 なぜ、キングからのCDはいい音なのか?
なぜ、キングからのCDはいい音なのか?
その理由のひとつはこうだ:
昨年、キングは賢明にも、クリード本人、そしてCTIのほとんどのレコーディングを手がけたオリジナルのエンジニアであるルディ・ヴァン・ゲルダーに依頼をし、日本でのリリースのために何枚分かのオリジナル音源のリマスターをおこなっていたのだ。結果は最高の出来で、オリジナルのバイナルLPよりもさらにいいサウンドになってしまった。
テープに収録されている情報量は、アナログリリースに収めることができた情報量を上回るのだから、このような現象が起きても、なんの不思議もないのである。
デジタル時代の技術で優しくリマスターされ、よりよいステレオ環境で再生されれば、レコードよりもいい音がCDから流れてくるのである。(中略)
ではここで歴史を少し復習しておこう。
クリード・テイラーはA&Mの社員だった1967年にCTIを立ち上げている。もともとはA&Mの中にある独立レーベルだったのだ。
社の創設者のハーブ・アルパートとジェリー・モスは、Verveからジャズ・プロデューサーであるクリード引き抜いたときに、自分のレーベルを立ち上げてよいということを約束していた。
A&M時代のクリードの初期のリリースには、以下のような作品があった:
Wes Montgomeryの A Day in the Life 、 Down Here on the Ground, Antonio Carlos Jobimの Wave , Quincy Jones のWalking in Spaceなどである。
そして1969年、クリードとA&Mは袂を分かつことになる。
交渉の結果、CTIは独立した会社となり、A&M がそのディストリビューションを受け持つということになった。1960年代の終わりから1970年代にかけてのレコード産業では、全国の店頭までレコードを届ける、ディストリビューションという仕事がとても大切だった。工場から、消費者のもとへと製品を運ぶ、生命線だったからだ。
1969年から1979年にかけて、クリードは、大変エネルギッシュで、インスト部分がかつてないほどに豪華で、フィデリティー(音質)にこだわりまくった、まったく新しいジャズのかたちを生み出していった。
ディストーションを最小限に押さえ、曲ごとの情報量を最大に保つために、クリードとルディはLPの片面に最高18分の音楽しか入れないという方針を立てていた。
オリジナルのサウンドが極上品質だったのは、このためである。
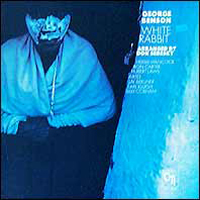 しかし、なんといっても、 CTIを有名にしたのは、その画期的なパッケージだった。
しかし、なんといっても、 CTIを有名にしたのは、その画期的なパッケージだった。
アルバムジャケットは見開きで、 そこにはカラーの豪華な写真が掲載された。その写真の撮影のほとんどは、ピート・ターナーという写真家が担当した。狙いは、リビングルームのインテリアの一部として成立するレコード・ジャケットを作ること。そして、大学生や若い大人たちの間で人気爆発中だった新しいハイ・ファイ・コンポで聞くにふさわしい、特別なサウンドの音楽を提供するということだった。
 もちろん、すべてのリスナーがCTIを好きになったわけではない。
もちろん、すべてのリスナーがCTIを好きになったわけではない。
ジャズファンの中には、いまだにCTIを認めないという人たちもいる。CTIのために、ジャズのジャズたる部分が置き去りにされたと、憤慨する純粋主義者もいた。
本来ジャズの持つ、とがったエッジを失わせ、新しく、よりクールな、ジャズ・ロック・フュージョンの動きに屈したと見る向きもいた。「スムーズ・ジャズ」と呼ばれる新ジャンルの台頭の責任もCTIにあるとするファンもいた。
しかし、愛そうが嫌おうが、CTI がジャズ・サウンドそのものを大きく変えてしまう力になったことに議論の余地はない。
クラシック音楽の要素をジャズ・ロック・フュージョンに取り入れ、新しいパッケージングやマーケティング戦略を通して、1980年代のジャズを牽引した。CTIはまた、ハウスバンドを結成し、アーティストたちに個性的なサウンド作りの自由なスペースを十分に与えることによって、主要なジャズ・ミュージシャンたちに常に仕事を与え続けていた。
 ようするに、CTIは、リスナーに対して、既存のものよりもよりジューシーで、親しみやすい音楽を提供したということだろう。
ようするに、CTIは、リスナーに対して、既存のものよりもよりジューシーで、親しみやすい音楽を提供したということだろう。
ただし、CTIからリリースされたすべてのアルバムが今日まで語り継がれているわけではない。クリードももちろん、それを認めている。
しかし、時を越えて残ってきたアルバムたちは魔力にあふれ、ビニール盤には入りきらなかった音であふれている。キングからの再発では、オリジナルでは聞こえていなかった音が実はたくさんあったということがわかるし、ほとんどの作品が現代でも十分に通用する素晴らしい音楽だということも実感できるのである。
キングレコードからの再発において、クリードとルディは、初出のLPレコードではわからなかった細部のニュアンスまで、聞かせることに成功している。そもそも、ここで使われたテクノロジーそのものが、一段上を行くものなのだが、その詳細はまた後日。ひとまずは、新しいキングのCTIシリーズのCDの中から、私のお気に入りを紹介するとしよう。本題に入る前に、我がオフィスのオーディオ環境についてお伝えしておこう: 音楽はすべて、外付けHDDのiTunesライブラリーに保存している。
 そこから同軸ケーブルでBenchmarkのDAC1 [写真]、アーカムのレシーバー、B&Wモニタースピーカーへとつないでいる。
ひとことで言うなら、DAC1の高い情報量、解析度が、エキサイティングなリスニング体験をもたらしてくれる環境だ。HDDへの読み込みには、appleロスレスエンコーダーを使用し、CD音源と同等レベルの音質を保つようにしている。
そこから同軸ケーブルでBenchmarkのDAC1 [写真]、アーカムのレシーバー、B&Wモニタースピーカーへとつないでいる。
ひとことで言うなら、DAC1の高い情報量、解析度が、エキサイティングなリスニング体験をもたらしてくれる環境だ。HDDへの読み込みには、appleロスレスエンコーダーを使用し、CD音源と同等レベルの音質を保つようにしている。
さて、このプロジェクトだが、その成功の裏には、キングレコードのプロデューサーのセンスの良さがあったことは言うまでもない。CTIの2トラックのマスター音源を、オリジナルの丸みを帯びた暖かさをそのままに、デジタル時代に運ぶためには、その「運び人」としてクリードとルディを任命するしかない、と彼は考えたわけだ。まったく3人とも、見事な仕事をやってくれたものだ。結果として表れたのは、オリジナルを越えるほどの音楽の情報量だった。
私のベスト11を選んでみた…
 Red Clay (1970). フレディー・ハバードとジョー・ヘンダーソンのトランペットとサックスと同じくらいにはっきりと、後ろのトリオの音が聞こえる! これは嬉しい。ハービー・ハンコックのフェンダー・ローズ、ロン・カーターのベース、そしてレニー・ホワイトのドラム。みんなが平等に重要なメンバーとして、このジャズ・ロック・フュージョン創生期のクラシックを奏でている。Red Clay, Suite Sioux ,Intrepid Fox のリフには、特に注目。まったく新しいエネルギーが加わっている。
Red Clay (1970). フレディー・ハバードとジョー・ヘンダーソンのトランペットとサックスと同じくらいにはっきりと、後ろのトリオの音が聞こえる! これは嬉しい。ハービー・ハンコックのフェンダー・ローズ、ロン・カーターのベース、そしてレニー・ホワイトのドラム。みんなが平等に重要なメンバーとして、このジャズ・ロック・フュージョン創生期のクラシックを奏でている。Red Clay, Suite Sioux ,Intrepid Fox のリフには、特に注目。まったく新しいエネルギーが加わっている。
 Sugar (1970). スタンリー・タレンタインのこのジャズ・ソウルの名作には、LPやCDの時にはここまではっきりとは存在していなかった、ホーンのまったく新しい質感が加わっている。タレンタインのサックスの高音にはスナップが効きまくっているし、フレディー・ハバードのトランペットも同様だ。ホーンたちの合間を縫って飛び出してくるロニー・リストン・スミスのエレクトリック・ピアノとオルガン、そしてビリー・ケイのシンバルの生き生きとした響きもいい。オリジナルのアルバムでは、Sugar, Sunshine Alley そして Impressionsの3曲だけがとりわけファンキーに、存在感を持っていた。でも今では、一曲一曲が輝いている。
Sugar (1970). スタンリー・タレンタインのこのジャズ・ソウルの名作には、LPやCDの時にはここまではっきりとは存在していなかった、ホーンのまったく新しい質感が加わっている。タレンタインのサックスの高音にはスナップが効きまくっているし、フレディー・ハバードのトランペットも同様だ。ホーンたちの合間を縫って飛び出してくるロニー・リストン・スミスのエレクトリック・ピアノとオルガン、そしてビリー・ケイのシンバルの生き生きとした響きもいい。オリジナルのアルバムでは、Sugar, Sunshine Alley そして Impressionsの3曲だけがとりわけファンキーに、存在感を持っていた。でも今では、一曲一曲が輝いている。
 Stone Flower (1970). A&M時代のクリードが手がけた、アントニオ・カルロス・ジョビンのレコーディングは数回分、存在する。独立CTI からのジョビンの第1弾では、優しく落ちてくる雨の音のような、彼の大人のボサノヴァと、アービー・グリーンの暖かく、フレンドリーなトロンボーンを聞くことができる。ジョビンのピアノが、フルート、アコースティック・ギター、あるいはストリングスと共に入ってくると、それはまるで打ち寄せる波のようだ。Children's Gameの際立つインストルメンテ−ションなどはその好例。ささやくようなカバサのリズムに守られた、ジョビンのフェンダー・ローズ が引き立つ、Andorhina もすてきだ。
Stone Flower (1970). A&M時代のクリードが手がけた、アントニオ・カルロス・ジョビンのレコーディングは数回分、存在する。独立CTI からのジョビンの第1弾では、優しく落ちてくる雨の音のような、彼の大人のボサノヴァと、アービー・グリーンの暖かく、フレンドリーなトロンボーンを聞くことができる。ジョビンのピアノが、フルート、アコースティック・ギター、あるいはストリングスと共に入ってくると、それはまるで打ち寄せる波のようだ。Children's Gameの際立つインストルメンテ−ションなどはその好例。ささやくようなカバサのリズムに守られた、ジョビンのフェンダー・ローズ が引き立つ、Andorhina もすてきだ。
 Montreux II (1970). 私の大好きなビル・エヴァンズアルバムのひとつ。スイスでのライブレコーディングである。このコンサート・レコーディングでのエヴァンズの演奏はあまりにも美しい。本作は彼のロマンティック時代の最後に近い時期のもので、これ以降のエヴァンズは、よりパーカッシッブな表現の時代へと移って行く。本アルバムに含まれるとりわけ素晴らしい作品としては、Alfie, How My Heart Sings, Peri's Scopeなどが挙げられる。リマスターされた本作では、エディー・ゴメズのベースと、ドラマー、マーティ・モレルのブラッシュワークが、非常に細かいところまで聞くことができて、嬉しい。 Peri's Scopeの前半部分で、特にそれが顕著だ。このリマスター版を聞くと、これが本当にエヴァンズの最も偉大なトリオのひとつだったのだということが、つくづくと実感できるのである。
Montreux II (1970). 私の大好きなビル・エヴァンズアルバムのひとつ。スイスでのライブレコーディングである。このコンサート・レコーディングでのエヴァンズの演奏はあまりにも美しい。本作は彼のロマンティック時代の最後に近い時期のもので、これ以降のエヴァンズは、よりパーカッシッブな表現の時代へと移って行く。本アルバムに含まれるとりわけ素晴らしい作品としては、Alfie, How My Heart Sings, Peri's Scopeなどが挙げられる。リマスターされた本作では、エディー・ゴメズのベースと、ドラマー、マーティ・モレルのブラッシュワークが、非常に細かいところまで聞くことができて、嬉しい。 Peri's Scopeの前半部分で、特にそれが顕著だ。このリマスター版を聞くと、これが本当にエヴァンズの最も偉大なトリオのひとつだったのだということが、つくづくと実感できるのである。
 Gilberto with Turrentine (1971). 1963年のGetz/Gilberto で、アストラッド・ジルベルトの歌声を初めてレコーディングしたのは、もちろん、クリードの仕事だった。The Girl From Ipanema が場外ホームランとなったことはいうまでもない。このアルバムでのジルベルトは、Promises, Promises からのバート・バカラックのWanting Things や、映画Lovers and Other Strangers からのFor All We Know (これはポルトガル語で)などを歌っている。しかし、今回、特別に嬉しいのは、ジルベルトのティッシュのような柔らかな声が、ストリングスやギター、そしてその他のさまざまな楽器たちと反応し合う様子を、しっかりと聞くことができることだ。
Gilberto with Turrentine (1971). 1963年のGetz/Gilberto で、アストラッド・ジルベルトの歌声を初めてレコーディングしたのは、もちろん、クリードの仕事だった。The Girl From Ipanema が場外ホームランとなったことはいうまでもない。このアルバムでのジルベルトは、Promises, Promises からのバート・バカラックのWanting Things や、映画Lovers and Other Strangers からのFor All We Know (これはポルトガル語で)などを歌っている。しかし、今回、特別に嬉しいのは、ジルベルトのティッシュのような柔らかな声が、ストリングスやギター、そしてその他のさまざまな楽器たちと反応し合う様子を、しっかりと聞くことができることだ。
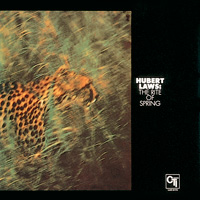 Rite of Spring (1971). 発売当時は、あまり気に留めていなかったアルバムだった。だが、今聞いてみると、ヒューバート・ローズのジャズ・クラシック的な演奏がとてもウッディーで、心温まることに気づいた。Pavane, Rite of Spring, Syrinx, そしてBrandenburg Concerto No. 3 の第一、二楽章まで、ボブ・ジェームズのエレクトリック・ピアノ、アイアートの光り輝くパーカッション、ロン・カーターの鼓動のようなベース、そしてその他の楽器たちの上を、ローズはまるで羽のような軽さで浮遊して行く。私にとって、今回のリマスターは、思いがけなく嬉しい、新発見、再発見をもたらしてくれる。
Rite of Spring (1971). 発売当時は、あまり気に留めていなかったアルバムだった。だが、今聞いてみると、ヒューバート・ローズのジャズ・クラシック的な演奏がとてもウッディーで、心温まることに気づいた。Pavane, Rite of Spring, Syrinx, そしてBrandenburg Concerto No. 3 の第一、二楽章まで、ボブ・ジェームズのエレクトリック・ピアノ、アイアートの光り輝くパーカッション、ロン・カーターの鼓動のようなベース、そしてその他の楽器たちの上を、ローズはまるで羽のような軽さで浮遊して行く。私にとって、今回のリマスターは、思いがけなく嬉しい、新発見、再発見をもたらしてくれる。
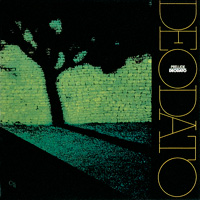 Prelude (1972). エウミリール・デオダードがリーダーとしてCTIで録音した初めてのアルバムは、大ヒットとなった。 高揚感あふれるAlso Sprach Zarathustraのコンガやホーンがたまらない。Spirit of Summer, Carly & Caroleのような、繊細な曲にも映える、デオダードのきっちりとしたフェンダー・ローズもいい。リマスター版では、ストリングの音が暖かさとしなやかさを増し、エレクトリック・ピアノとヒューバート・ローのフルートが、カーリー・サイモン、キャロル・キングに捧げるデオダードの軽いラテンのトリビュートに、美しい響きを加えている。
Prelude (1972). エウミリール・デオダードがリーダーとしてCTIで録音した初めてのアルバムは、大ヒットとなった。 高揚感あふれるAlso Sprach Zarathustraのコンガやホーンがたまらない。Spirit of Summer, Carly & Caroleのような、繊細な曲にも映える、デオダードのきっちりとしたフェンダー・ローズもいい。リマスター版では、ストリングの音が暖かさとしなやかさを増し、エレクトリック・ピアノとヒューバート・ローのフルートが、カーリー・サイモン、キャロル・キングに捧げるデオダードの軽いラテンのトリビュートに、美しい響きを加えている。
 Deodato 2 (1973). 個人的にはザ・ムーディ・ブルースの Nights in White Satin は あまり好きではなかったのだが、このアルバムのインストを聞いて、意見が変わった。Skyscrapers、Super Strutなど、ディスコが発明される前の時代の、生き生きとしたダンス・ナンバーも楽しい。ここでも、ルディのリマスタリングが、デオダードのフェンダー・ローズそしてビリー・コブハムのドラムの音から、あのエレクトロニックな感じを排除していて、細かいニュアンスまでもきっちりと捕まえてくれている。1970年代に子供時代を過ごした我々にとっては、電子ピアノをこの音で再び聞けることは、至福の体験である。
Deodato 2 (1973). 個人的にはザ・ムーディ・ブルースの Nights in White Satin は あまり好きではなかったのだが、このアルバムのインストを聞いて、意見が変わった。Skyscrapers、Super Strutなど、ディスコが発明される前の時代の、生き生きとしたダンス・ナンバーも楽しい。ここでも、ルディのリマスタリングが、デオダードのフェンダー・ローズそしてビリー・コブハムのドラムの音から、あのエレクトロニックな感じを排除していて、細かいニュアンスまでもきっちりと捕まえてくれている。1970年代に子供時代を過ごした我々にとっては、電子ピアノをこの音で再び聞けることは、至福の体験である。
 Baltimore (1978). このアルバムのニナ・サイモンのうしろには、なんと30人以上のバック・ミュージシャンたち、そして8人のバック・シンガーが控えている。でも、そんな大げさな様子などひとつも感じさせないほど、ニナの薫り高いコーヒーのような歌声は堂々と主役を張っている。かつてのCDでは、オーケストラの音が小さいような感じもしたのだが、今回は違う。演奏が見事に彼女の声を取り巻き、包んでいるのだが、邪魔しているところはひとつもないという感じだ。 My Father, ホール・アンド・オーツの Rich Girl 、そして If You Pray Right はどれもしびれる、元気の出る音楽だ。
Baltimore (1978). このアルバムのニナ・サイモンのうしろには、なんと30人以上のバック・ミュージシャンたち、そして8人のバック・シンガーが控えている。でも、そんな大げさな様子などひとつも感じさせないほど、ニナの薫り高いコーヒーのような歌声は堂々と主役を張っている。かつてのCDでは、オーケストラの音が小さいような感じもしたのだが、今回は違う。演奏が見事に彼女の声を取り巻き、包んでいるのだが、邪魔しているところはひとつもないという感じだ。 My Father, ホール・アンド・オーツの Rich Girl 、そして If You Pray Right はどれもしびれる、元気の出る音楽だ。
 Big Blues (1978). アート・ファーマーとジム・ホールは数多くの共作を残している。このリマスター版のいいところは、楽器のひとつひとつ、すべてを聞くことができることだ。特に感激するのが、ドラマーのスティーブ・ガッド、そしてヴァイビストのマイク・マイニエリの演奏。ファーマーのホーンの貴重なトップを、ほかの楽器のディテールを一切失わない状態で聞けるのも、うれしい。
Big Blues (1978). アート・ファーマーとジム・ホールは数多くの共作を残している。このリマスター版のいいところは、楽器のひとつひとつ、すべてを聞くことができることだ。特に感激するのが、ドラマーのスティーブ・ガッド、そしてヴァイビストのマイク・マイニエリの演奏。ファーマーのホーンの貴重なトップを、ほかの楽器のディテールを一切失わない状態で聞けるのも、うれしい。
 Fus e One (1980). リーダーであるベーシストのスタンリー・クラークが大暴れする、ポスト・ディスコファンクのアルバム。クラークのベース、そしてテナー・ベースのスナップのひとつひとつがはっきりと聞こえる。ジョー・ファレルのテナー・サックスも素晴らしい。思いがけず大当たりしたこのアルバムで、1980年代のアダルト・コンテンポラリー・ブームの幕は切って落とされた。
Fus e One (1980). リーダーであるベーシストのスタンリー・クラークが大暴れする、ポスト・ディスコファンクのアルバム。クラークのベース、そしてテナー・ベースのスナップのひとつひとつがはっきりと聞こえる。ジョー・ファレルのテナー・サックスも素晴らしい。思いがけず大当たりしたこのアルバムで、1980年代のアダルト・コンテンポラリー・ブームの幕は切って落とされた。
JazzWaxメモ:
 今回のキングのCTIシリーズに含まれる残りの9枚はこちら: Milt Jacksonの Sunflower, Jim Hallの Concierto, Ron Carterの All Blues そして Spanish Blue, Hubert Lawsの Chicago Theme, Lalo Schifrinの Towering Tacata, Airtoの Fingers, Patti Austinの End of a Rainbow そしてGeorge Bensonの In Concert at Carnegie Hall。
今回のキングのCTIシリーズに含まれる残りの9枚はこちら: Milt Jacksonの Sunflower, Jim Hallの Concierto, Ron Carterの All Blues そして Spanish Blue, Hubert Lawsの Chicago Theme, Lalo Schifrinの Towering Tacata, Airtoの Fingers, Patti Austinの End of a Rainbow そしてGeorge Bensonの In Concert at Carnegie Hall。
以下に、今回のリマスターに使用されたテクノロジーについて、アマゾンに掲載されたキングのCDの解説を紹介しておく。
"日本限定 SHM プレス。ルディ・ヴァン・ゲルダーによるリマスタリング。SHM-CD [スーパー・ハイ・マテリアル CD] フォーマットは、特殊なポリカーボネイト・プラスティックを使用して音質を向上させたもので、この製造プロセスは、JVCとユニバーサル・ミュージック日本によってLCDディスプレイの研究中に発見された。SHM-CDの特徴は、ディスクのデータ側面の透明性で、これによってCDプレイヤーのレーザーヘッドがより正確にCDデータを読み取ることを可能とした。なお、SHM-CD形式CDは、標準のCDプレーヤーと完全に互換性がある。"
アメリカのジャズ・ブログ jazz wax から、筆者の許諾を得て掲載。こちらには良い写真が沢山ありますので是非一度ご覧下さい。
http://www.jazzwax.com/
